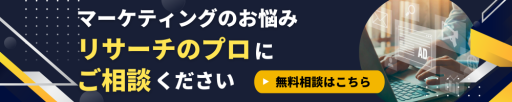新しい商品を市場に投入することは、多くの企業にとって大きな挑戦です。
しかし開発された新商品のうち、そのほとんどが市場に定着することなく姿を消していきます。実際にヒット商品として成功する確率は、わずか数%とも言われています。
商品開発の成功確率を高めるためには、事前のリサーチが欠かせません。
本記事では、市場の動向や消費者のインサイトを把握するマーケティングリサーチと、実際の使い勝手やユーザー体験を検証するUXリサーチ(デザインリサーチ)を組み合わせることで、「売れる商品」かつ「選ばれる商品」 を開発するためのヒントを探っていきます。
目次
商品開発のアプローチ
商品開発には大きく分けて2つのアプローチがあります。
- マーケットイン(Market-In):市場のニーズを調査し、それに基づいて商品を開発する考え方。
- プロダクトアウト(Product-Out):企業が持つ技術やアイディアを活かして、商品を作り出し、市場に売り込む考え方。プロダクトアウトのアプローチでもヒットにつながった商品は多くあります。しかし、市場のニーズを無視して企業視点だけで開発すると、消費者に受け入れられないリスクがあることも事実です。
一方で、マーケットインの考え方を取り入れることで、「消費者が本当に求めている商品」 を開発することができ、失敗のリスクを抑えることができます。
マーケットインとプロダクトアウトの違いについて詳しくはこちら
マーケティングリサーチやUXリサーチが不足している場合のリスク
商品開発の成功には、市場ニーズやユーザーの行動への理解を深めることが重要です。マーケティングリサーチやUXリサーチが不足していると、以下のようなリスクが生じてしまう可能性があります。
直感や社内意見に頼ってしまう
経営層や開発チームの経験則や直感、社内の意見だけで商品を開発するケースは意外と少なくありません。しかし、企業の視点と消費者の視点にはズレがあることが多く、「売れるはず」と思って、客観的な意見なしで開発した商品が市場で全く受け入れられないこともあります。
流行や消費者の価値観が変化し続ける中で、本当にニーズがあるのかを確かめることなく、過去の成功事例に頼って商品化してしまうのは危険です。
そもそもターゲットが明確でない
商品開発の初期段階でターゲットが明確でないと、誰に向けた商品なのかが曖昧になり、結果的に「誰にも刺さらない」商品になりかねません。
年齢・性別・ライフスタイル・価値観など、ターゲットのペルソナを明確にしないまま開発を進めると、訴求ポイントがブレてしまい、販売戦略も効果的に立てられなくなります。
使いにくい・魅力を感じにくい、UI/UXで顧客に選ばれない
商品が売れるかどうかは、「どれだけ市場ニーズがあるか」だけでなく、「どれだけ使いやすく、魅力的か」も重要です。特にデジタルサービスや家電製品では、UX(ユーザーエクスペリエンス)の良し悪しが購入や継続利用の決め手になります。
開発の段階でリサーチが不足していると、「機能は優れているが、使いにくい」「デザインにこだわったが、直感的に操作できない」 などの問題が発生し、既存ユーザーの離脱をも招きます。
UIやUXについて詳しくまとめた資料はこちらからご覧いただけます
商品開発に活用すべきリサーチのポイント
これらのリスクを避けるためには、マーケティングリサーチとUXリサーチの両方を取り入れ、データに基づいた商品開発を行うことが重要です。次の章では、具体的にどのようなリサーチ手法を活用するかを解説していきます。
市場トレンド・ニーズの把握やアイディア創出
市場ニーズやトレンドの把握には、次のようなリサーチが有効です。
デスクリサーチ
オープンソースの情報(各種統計、インターネット、新聞、雑誌、図書等)を元に、ヒット商品や各世代のトレンドなど、デスクリサーチでも有効な情報は発見できます。電通マクロミルインサイトでは、価値ある情報をテーマごとにキュレーションしたレポートなどを作成することも可能です。
エキスパートリサーチ
自社が今まで手掛けていない新市場に進出する際には、有識者ヒアリングもおすすめです。各専門領域の有識者や、大学・研究機関、業界誌などのジャーナリストなど、専門家の立場から業界や商品・サービス等についての意見の収集や他社事例の収集をヒアリングするインタビュー調査です。
アクセスが難しい一次情報や社外の知見、競合情報を得ることで、経営戦略・事業戦略の立案や新規事業開発などをよりスムーズに進めることができます。
ワークショップ
デスクリサーチなどを通じて得られたトレンドのヒントをもとに、アイディア創出のためにワークショップを行う場合も多くあります。
ただ各自が事前準備をせずにワークショップを行っても、なかなか創発的な意見は出にくいものです。
弊社では、生活者起点でのアイディアや商品サービス開発につながる、リサーチ会社だからこそご提供可能なメソッドやワークショップの進行をスムーズにできるツールなどを提供して、効果的なワークショップ運営のノウハウと実績があります。
ウェルビーイングな商品開発のヒントに使えるツール:アイディア創発のヒント集「Happy Brain Card」のご紹介について詳しくはこちら
競合分析
類似商品との差別化を明確にするためにも、次のような競合分析を行うことも重要です。
インターネットリサーチ(定量調査)
消費者が競合商品やサービスに対して抱いているイメージや、競合商品に対する評価や満足度などの収集にインターネットリサーチは適しています。オンラインで調査を実施することで、多くの消費者から短期間でデータを集めることが可能です。
エキスパートリサーチ
競合を含む市場動向などの状況をヒアリングしたい場合は、各分野の有識者へのヒアリングも有効です。
各専門領域の有識者や、大学・研究機関、業界誌などのジャーナリストなど、専門家の立場から業界や商品・サービス等についての意見の収集や他社事例の収集をヒアリングする調査です。
アイディア段階や上市前のコンセプト受容テスト
開発に着手、上市する前に、商品の基本的なコンセプト(ターゲット、特徴、価格など)やプロトタイプを消費者に提示して評価を収集し、消費者の期待と合っているか、改良すべき点は何かを明確にすることでターゲットに受け入れられやすい商品開発が可能となります。
このように、コンセプト段階でのテストを行うことで、開発の方向性をより精度高く調整できます。
インターネットリサーチ
インターネットリサーチでは、オンライン上に複数のコンセプト案を提示し、ターゲットの反応を探ることが可能です。その際に、コンセプトの利用意向(使いたいと思えるか)、新規性(真新しさを感じるか)の2軸で評価をするなど、評価する軸を決めておき調査項目に反映することで、定量的な評価を得ることが可能です。
インタビュー(グループインタビュー/デプスインタビュー)
インタビューなどの定性調査で、ターゲットとなる消費者にコンセプトを提示して、商品の魅力が伝わるか、どこを改良すればよいか、などを確認することも有効です。
オンライン調査では測れない、言語化できない表情や言葉のトーンなどの反応も確認できます。
インタビュー調査には、4~6名の調査対象者を一同に集め座談会形式で実施するグループインタビューと、デリケートなテーマを扱ったり一人一人の行動や価値観をヒアリングするのに向いているデプスインタビューがあります。
グループインタビューについて詳しくはこちら
デプスインタビューについて詳しくはこちら
ホームユーステスト
開発途中の試作品などを調査対象者に実際の生活の中で利用してもらい、意見や感想などを収集するリサーチ手法です。
一定期間のテストを依頼することができるため、利用開始時点から、中間、終了期など時間的な変化についても情報を収拾できます。
日用品や調理器具など、家庭で実際に利用しないと評価が取りにくい商品でも調査が可能です。
ユーザビリティテスト
商品開発において、単に市場のニーズを把握するだけでなく、「実際に使ったときの体験(UX)」を最適化することも重要です。特に、デジタルサービスや家電製品では、UXの良し悪しが購買意欲やリピーター獲得に大きく影響します。
UX(ユーザーエクスペリエンス)リサーチとは、「商品が使いやすいか」「ユーザーがストレスを感じないか」を調査し、課題点があった場合に、それを改善するプロセスで効果的です。デジタル商品(アプリ・ECサイト)だけでなく、家電や日用品など、物理的な製品の操作性にも応用できます。
・ユーザーがスムーズに使える設計になっているか?
・直感的に操作できるUI/UXか?
・期待した機能やサービスをすぐに見つけられるか?
こうした視点でリサーチを行い、実際の使用感に基づいた改善を加えることで、「購入はしたけれど、使いにくいからやめた、次はもう購入しない」 という離脱を防ぎます。
ヒューリスティック分析
消費者調査では提示しにくい、初期のデザインスケッチやアイディア、モックへの評価が必要な場合には、専門家が一連のヒューリスティック(経験則に基づいた原則)を用いてウェブサイトやアプリのワイヤーフレーム、またはプロトタイプなどを評価し、ユーザビリティの問題点や改善のための提案を行います。
価格・販売戦略の最適化
どれだけ優れた商品でも、価格設定や販売戦略が適切でなければ売れません。 価格が消費者(ターゲット)の感覚に合わなかったり、適切な販売チャネルを選ばなかったりすると、購買につながらない可能性があります。価格・販売戦略の最適化のために下記のようなリサーチが有効です。
プライシングリサーチでは、消費者がどの価格帯で価値を感じるのかを調査します。主な手法には以下があります。
PSM分析(価格感度測定)
消費者が「この価格なら買いたい」「この価格は高すぎる」と感じるポイントを数値化し、適正価格帯を導き出す手法です。
✔ 活用例: プレミアムブランドでPSM分析を実施し、「5,000円以上では高すぎるが、2,500円以下だと品質に不安を感じる」ことが判明し、最適価格を3,800円に設定。
コンジョイント分析(価値の優先順位を測定)
消費者が商品選択において、どの要素(価格・機能・デザインなど)を最も重視するのかを分析し、価格戦略に活かす手法。
✔ 活用例: 新しいノートPCの価格設定を行う際、「バッテリー持ち」「軽量」「価格」のどれが最も購入判断に影響を与えるかインターネットリサーチを通じて調査。
商品開発のためのマーケティングリサーチなら電通マクロミルインサイトにお任せください
幅広い知識や生活者のニーズを捉えるスキル、クリエイティブな発想が求められる商品開発。
市場に受け入れられる商品を開発するためには、いかに市場や顧客の声を収集・反映できるかが大きなカギになります。
また、商品販売した後も、検証や改善を繰り返していく必要があります。
商品開発に関わる市場調査やマーケティングリサーチをお考えなら、電通マクロミルインサイトにご相談ください。
マーケティングリサーチのセミナーや自主調査企画も実施。