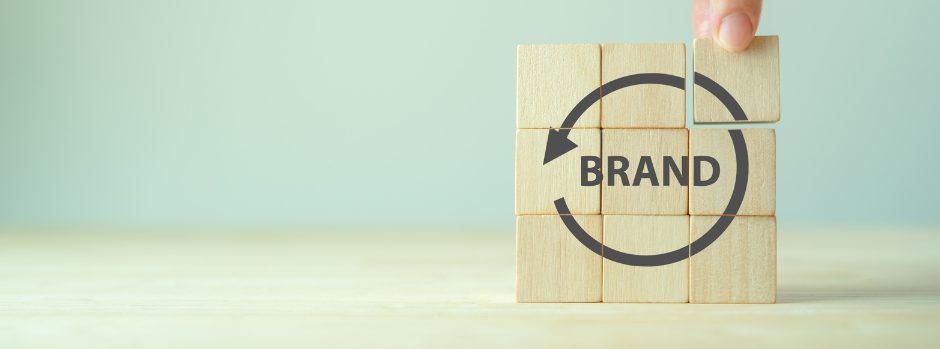目次
リブランディングとは
リブランディングとは、市場環境の変化に適応するために、ブランドのイメージなどを再構築して、新たな価値を創造する戦略です。企業や商品のブランドは一度確立すれば永続するものではなく、消費者の価値観の変化、競争環境の変化などにより、適切なアップデートが求められます。
ブランディングとの違い
ブランディングとリブランディングは似た概念ですが、「新規ブランドの構築」か「既存ブランドの再構築」か、という点で大きく異なります。
ブランディングは、企業や商品を市場に認知させ、独自の価値を確立するための戦略です。新規事業や新商品を展開する際に、市場でのポジショニングやターゲット層を明確にし、一貫したブランドメッセージを構築することが求められます。
一方、リブランディングは既存のブランドを見直し(再構築して)、市場環境の変化に適応させることが目的です。ブランドの認知度があるものの、ターゲットとのズレが生じたり、競争優位性が薄れたりした場合に、デザインやメッセージを刷新し、新たなブランド価値を生み出すために実施します。
つまり、ブランディングが「ゼロからのブランド確立」であるのに対し、リブランディングは「既存ブランドの課題を解決し、新たな方向へ進化させる」プロセスという違いがあります。
なぜリブランディングが必要なのか?
1. 市場の変化:競争環境・トレンドの変化・DXの影響
新規参入企業の増加や技術の進化など、市場は常に変化しています。
特にデジタル技術の進化(DX)は、消費者の購買行動や情報収集の方法を大きく変えています。従来のブランド戦略が通用しなくなるケースも多く、時代の変化に合ったリブランディングが必要となります。
2. ターゲット層の変化:Z世代の台頭・消費者の価値観の変化
近年、Z世代の価値観や購買基準がマーケットに大きな影響を与えています。
タイパ意識やエシカル消費、SNSでの共感性など、従来のマーケティング手法が響きにくい層への対応が求められています。リブランディングを通じて、Z世代やアルファ世代といった、各ターゲットに適したメッセージやブランド体験を再設計することが重要です。
3.インナーブランディング、採用ブランディングの強化
ブランドは「企業の約束」であり、それを体現するのは商品・サービスだけでなく、従業員も同じです。
時代や戦略の変化に合わせてブランドの再定義を行うことで、ミッションやバリューが明確になり共通の価値観をもって業務に取り組めるようになり、「自分の仕事の意味」や「社会への貢献実感」が高まり、モチベーション向上につながります。
また、働くことへの価値観も変化している中で、「給与」や「安定性」だけではなく、「やりがい」「社会貢献」「共感できるミッション」などが重視されるようになっています。企業としてのリブランディングによって価値観を明確に打ち出すことで、新しい世代の求職者とのマッチング精度が高まり、採用力が向上します。
このように、リブランディングは企業や商品が持続的に成長し、市場での競争力を維持するために欠かせない戦略です。
コーポレートリブランディングとプロダクトリブランディング
リブランディングは、大きく「コーポレートリブランディング」(企業全体のブランド刷新)と「プロダクトリブランディング」(特定の商品・サービスのブランド刷新)に分かれます。
例えば、企業のミッションやビジョンの変更、ロゴやコーポレートカラーの見直しはコーポレートリブランディングにあたり、新商品のターゲット変更やデザインリニューアルはプロダクトリブランディングの一例です。
成功するリブランディングには、市場やターゲットの深い理解が不可欠です。単なるデザイン変更にとどまらず、ブランドの根幹にある価値を見直し、消費者との新たな関係を築くことが重要となります。
コーポレートリブランディング(企業全体のブランド刷新)
コーポレートリブランディングとは、企業全体のブランドイメージを刷新し、企業価値の向上や社会的信用の確立が目的となります。
企業のブランドは、単なるロゴやスローガンといった表面的なものにとどまらず、ステークホルダー(顧客・投資家・従業員・取引先)との関係を築く基盤となります。
コーポレートリブランディングにより、企業の存在意義や強みや独自性を再定義し、市場でのプレゼンスを強化することで、投資家や金融機関からの信頼度(信用度)が高まり、採用ブランディングの強化にもつながります。
コーポレートリブランディングの事例 :湖池屋
湖池屋は、スナック市場の成熟化の中で売上低下に直面し、2016年に新経営体制を導入したタイミングで、リブランディングを開始しました。
今までのものを捨てて新しいものに生まれ変わるのではなく、 創業当初の「まるで料理をつくるように」「業界最高品質のものを」という原点の理念に立ち返り、高品質なプレミアムラインの商品開発に注力しました。
その象徴として2017年に「湖池屋プライドポテト」を発売し、使用する原料の選定や、製法、味づくりといった商品の中身はもちろん、パッケージのデザインや形状、価格帯を見直し、斬新なパッケージデザインとインパクトのあるコミュニケーション戦略を展開しています。
結果、発売から1カ月で品切れ状態となるなど、大きな話題を呼びました。このリブランディングにより、湖池屋は独自のポジションを確立し、新たなファン層の獲得に成功しました。
参照:
・“伝えるべき魅力”に集中したことで話題化に成功 ―新生・湖池屋のリブランディング戦略―
・湖池屋プロジェクトストーリー
プロダクトリブランディング(特定の商品・サービスのブランド刷新)
プロダクトリブランディングとは、特定の商品やサービスのブランドを見直し、市場競争力を強化する戦略です。
市場のトレンドや消費者ニーズの変化に対応し、ブランド価値を高めることで、売上向上や競争優位性の確立を目指します。
単なる商品改良にとどまるのではなく、ブランドの印象やメッセージを再構築することが不可欠です。リブランディングを通じて、商品価値を明確に伝え、消費者の認知度や選好を高めることで、市場での存在感を強化し、売上の向上につなげます。
リブランディングを必要とする状況
・既存商品の売上低迷:市場シェアが縮小し、競争力が低下している場合
・新ターゲット層の獲得:消費者のライフスタイルや嗜好の変化に対応し、新たな市場・ターゲットを開拓
・競争優位性の確立:他社製品との差別化を強調し、ブランドポジショニングを再定義
リブランディングの一環となる施策
・商品パッケージやロゴの変更
・プロモーション戦略の再構築
・価格戦略やターゲット市場の再設定
・商品のUI/UXの見直し
商品リブランディングの事例:DOLLY WINK
DOLLY WINKは、かつてギャル文化の象徴として大ヒットした“つけまつげ”ブランドですが、ナチュラルメイクの流行やマツエクの普及で売上が激減したのを契機に、2019年にリブランディングを実施。
高い技術力・商品クオリティーと日本で初めてつけまつげを発売したという歴史的背景を再評価したうえで、ターゲットへのリサーチを重ねて「手間をかけずにナチュラルに盛りたい」「多様な選択肢の中から自分らしさを選びたい」という2つの令和女子のインサイトを導き出しました。
そのインサイトから、市場の8割を占める「つけまつげ離脱者/未使用者」に対して、「10秒マツエク」という新コンセプトと、16種にも及ぶ商品ラインアップ、さらにアイコニックなイラストが目を引くパッケージデザインを開発し、製品の価値を再訴求しました。
その結果、「オワコン」とされた市場で再注目され、ブランドの再生に成功しました。
参照:オワコンだった“つけま”が復活。令和女子にヒットするものづくりとは?
リブランディングのステップにおけるマーケティングリサーチの活用
リブランディングを成功させるためには、戦略的なアプローチと徹底した準備が不可欠です。
単なるロゴ変更やデザインリニューアルといった表面的な変更ではなく、ブランドの本質・価値を見直し、市場でのポジショニングを再構築することが求められます。
現状分析と課題抽出
1. 市場トレンドや消費者インサイト分析
リブランディングを進めるうえで最初に行うべきことの一つが、市場トレンドの把握です。
ブランドをどのように再構築すべきかを判断するためには、今、世の中で何が求められているのかを正確に捉える必要があります。
・市場規模や成長率:業界全体の動向や今後の成長性を分析
・消費者のニーズ・嗜好の変化:ターゲット層の価値観や購買行動の変化を把握
まずデスクリサーチを通じて、業界全体の動きや競合のブランディング戦略、トレンドワード、ヒット商品に共通しているテーマなどを俯瞰的に把握します。
加えて、アンケートなどの定量調査を用いて、消費者の意識や行動の変化を数値で捉えることが、リブランディングの出発点です。
特に、Z世代やアルファ世代といった若年層は、それまでの世代とは異なる価値観を有しており、世代への理解や変化の兆しの確認を継続的に行う必要があります。
現状のブランドイメージや認知度の把握
リブランディングを成功させるためには、現状、ブランドがどのように認知され、どのようなイメージを持たれているのかを正しく把握することが不可欠です。このステップで活用されるのが、定量調査と定性調査です。
定量調査では、インターネット調査などを活用して、ブランドの認知度、好意度、想起率などを数値で把握することでき、自社ブランドが市場内でどの程度知られているか、どのように評価されているかを客観的に測定することが可能です。
一方、定性調査では、インタビュー調査などを活用して、ブランドに対する印象や感情を言語化し、何に影響を受けてどのように変化したのかなど、数字だけでは見えない消費者の「本音」や深層心理を探ることが可能です。
これらの調査結果を組み合わせることで、ブランドの強みや改善点を立体的に把握でき、何を残し、何を変えるべきかを判断するための確かな土台となります。リブランディングの方向性を見極めるうえで、非常に重要なプロセスです。
競合比較による差別化ポイントの特定
リブランディングでは、自社ブランドが市場の中でどのようなポジションにあるのかを理解し、競合との差別化ポイントを明確にすることも重要です。そのために欠かせないのが、定量調査による競合比較です。
定量調査を活用することで、自社以外の複数ブランドに対する認知度、好意度、利用意向、イメージ項目(例:信頼性・先進性・親しみやすさなど)を数値で比較することができます。これにより、競合に対して自社が強みを持っているポイントや、逆に劣っている部分が明確になります。
たとえば、「品質」で競合に勝っているが、「トレンド感」では劣っている、というような具体的な差異が見えることで、自社のリブランディングでどの価値を強化・打ち出すべきかの判断材料となります。
定量的な競合比較は、感覚や思い込みに左右されない、客観的で説得力のある戦略立案を可能にします。
新コンセプト・デザインの評価
新たに設計したブランドコンセプトやロゴ、商品のパッケージやネーミング、デザインなどが、ターゲットに正しく伝わり、魅力的に受け止められるかを事前に検証することは重要です。
特に短期的なインパクトよりも長期的な共感を目指すリブランディングにおいて、事前検証は欠かせません。
アンケート調査(定量)を活用する場合は、複数の案(ロゴやパッケージデザインなど)を提示し、「好感度」「わかりやすさ」「購入意向」などを数値で比較します。消費者の直感的な反応を数値で把握でき、最も支持される案を明確にできます。
また、商品リニューアルに関わる場合、実際に消費者に使用・体験してもらったうえで、使い勝手やパッケージの印象、購入意欲などを評価してもらうホームユーステスト(HUT)は、特に食品や日用品など、実使用が価値に直結する商品に有効です。
他にも、ブランドの新しいポジショニングやコンセプト案に対して、「共感できるか」「ブランドらしさがあるか」「購買につながるか」などを確認するコンセプトテストも重要です。消費者視点での“響く表現”を見極めるうえで、必須のプロセスです。
UX・UI評価
UX(ユーザーエクスペリエンス)およびUI(ユーザーインターフェース)といった視点も、顧客満足度やブランド体験の向上に効果的です。リブランディングにおいて、単に見た目を刷新して美しいデザインにするだけでなく、「使いやすさ」「わかりやすさ」「心地よさ」といった体験全体を見直すことが、現代のブランドには求められています。
コーポレートリブランディングの一環で、Webサイトやアプリをリニューアルする際にも、ユーザビリティが劣っているとブランドイメージがマイナスにつながりかねません。
インタビューやユーザビリティテストを通じて、実際の利用シーンにおける不満や課題点を可視化することができます。
ヒューリスティック分析では、専門家の視点でwebサイト・アプリ・プロダクトのユーザビリティを客観的に評価することも可能です。
消費者にとって“心地よい”体験を提供できているかを客観的に把握し、改善の糸口を見出というのも、現代に求められるリブランディングの姿勢です。
リブランディング施策の効果測定
リブランディングは施策を「実行して終わり」ではなく、その成果を検証し、必要に応じて改善を重ねていくプロセスも重要です。
ブランド指標の変化を継続的にトラッキングし、施策実行の成否を判断できる体制を整えることが理想です。
ブランド刷新がターゲットにどう受け止められているか、施策が実際の行動変容につながっているかは、短期的な売り上げの変化だけでは判断できません。
ブランドの価値や印象は徐々に浸透していくため、中長期での指標追跡と定点観測が必要になります。
リブランディング前後でのブランド認知度や好意度、ブランドイメージの変化を定期的に数値で確認したりブランドリフトで確認していくことが必要です。
リブランディングにおけるマーケティングリサーチをお考えなら電通マクロミルインサイトにご相談ください
マーケティングリサーチは、感覚的・表層的になりがちなリブランディングを、顧客視点とデータに基づいて戦略的に進めるための羅針盤になります。ブランドの方向性に迷いがあるときこそ、客観的なリサーチが力を発揮します。